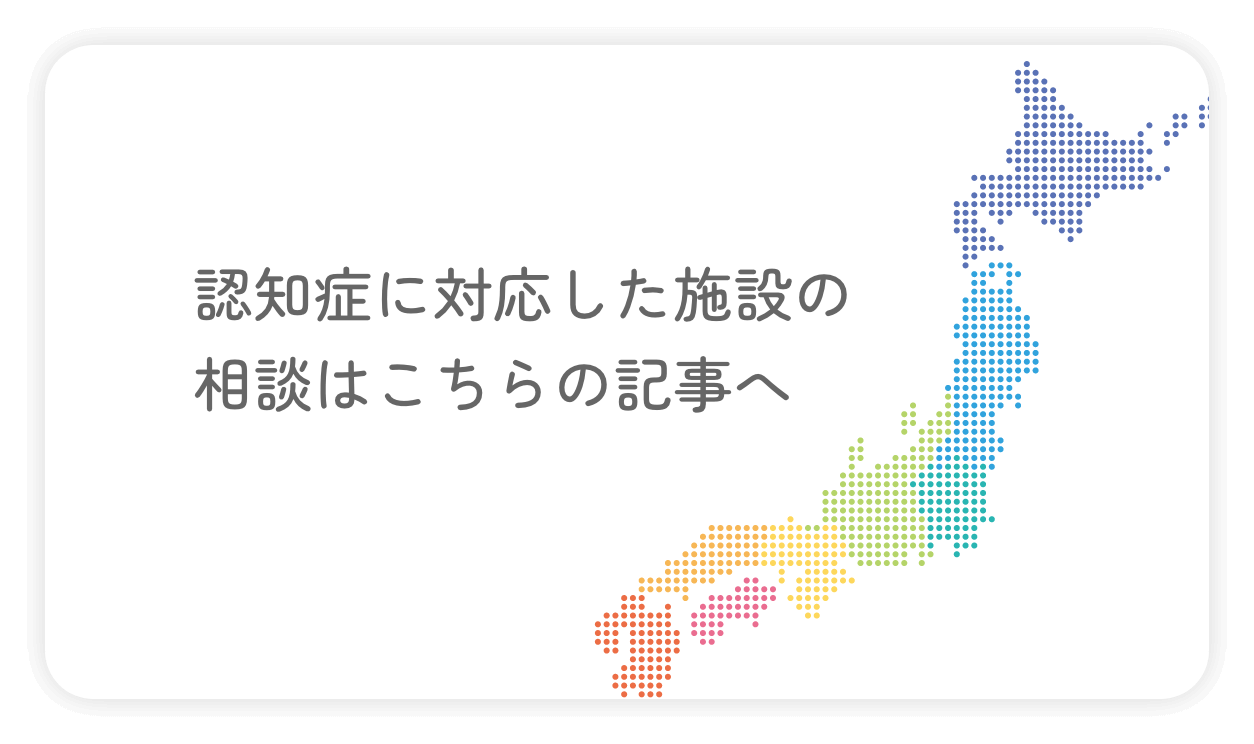認知症
認知症
 認知症
認知症
認知症で病院に入院できる!精神科に入院する3つの基準や期間を解説

「認知症でも病院に入院できるのだろうか」「入院期間や費用はどのくらいなのだろう」
このように悩んでいる方はいませんか。
認知症は、ひとたび発症すると完治するケースは少なく、介護が長期化することがあります。
さらに、認知症の症状が悪化して家族の介護だけでは手に負えなくなる場合もあるでしょう。
この記事では、認知症で病院に入院できるのか、基準など気になるポイントついてくわしくお伝えします。
認知症でも入院できるのかと不安を感じているあなたの悩みを解決できると幸いです。
Contents
認知症で病院に入院できる

認知症のケアは介護者にとって大変なものです。
認知機能の障害にともない、記憶力や判断力も低下します。
少し前のことを思い出せなかったり、これまでできていたことができなくなったりする症状です。
具体的には、料理中であったことを忘れて火の不始末が増えたり、トイレに行けず失敗したりします。
介護者の負担を軽減する体制づくりは、認知症の方を支えることにつながります。
その方法の1つが病院に入院することです。
ただし、認知症の方は必ずしも入院できるわけではありません。
認知症の方が入院する基準を知っておきましょう。
認知症で精神科に入院する3つの基準

認知症の多くは精神科への入院となり、主な基準は以下の「3つ」です。
精神保健福祉法に基づいて入院するケース
精神保健福祉法に基づく入院を「医療保護入院」といいます。
本人の同意が得られない場合でも、精神保健指定医が治療や入院が必要と判断し、保護者の同意があれば入院できます。
たとえば、以下のような症状があるときが医療保護入院の適応です。
- 薬の自己中断
- 妄想
- 暴力
- 徘徊
認知症の症状が悪化したときに、入院が必要と判断されます。
専門医が「入院が必要」と判断するケース
認知症の症状が悪化し、自分や人を傷つける恐れがあるときは「措置入院」となる場合があります。
これは、精神保健指定医2名以上による診察の結果、入院が必要だと判断した場合に都道府県知事が対応する入院の方法のひとつです。
措置入院では、警察官からの通報によって入院に至るケースが多いです。
精神医療審査会において入院の必要性についての審査がおこなわれ慎重に判断されます。
介護者の事情による入院するケース
介護者の事情によってレスパイトという形で一時的に入院できるケースもあります。
- 介護疲れ
- 冠婚葬祭
- 介護者の体調不良
- 介護者の出張や旅行
レスパイト入院の期間は病院によって異なります。
また、ベッドの空き状況により入院が難しいケースもあるため、事前に確認しましょう。
認知症で精神科に入院する期間や費用

入院を考えたとき、期間や費用のことも心配になる方も多いでしょう。
ここでは、一般的な目安をお伝えします。
認知症で精神科に入院する期間の目安
認知症の場合、入院期間が長期化する傾向があります。
令和2年度の厚生労働省の調査では、65歳以上でアルツハイマー型認知症を発症している方の入院は平均在院日数が「275日」でした。
入院の期間が長くなる要因は以下のとおりです。
- 栄養不良によるもの
- 心理面や身体面など本人の状態によるもの
- 認知症によるリハビリテーションの遅れによるもの
また、認知機能の低下にくわえて、暴言や暴力、幻覚などの心理・行動症状があります。
入院中の認知機能のさらなる低下や心理・行動症状で、治療が順調に進むことが難しいケースもあります。
認知症の入院費用
通常の入院と同じように、入院にかかる費用は以下のものがあります。
- 治療費
- 食費
- 差額ベッド代
- テレビ視聴や冷蔵庫の使用など
基本的に、認知症の治療費は医療保険適応であるため「1~3割の負担」です。
ただし、治療が長期化して高額となった場合には、公的支援制度が利用できるケースがあります。
- 高額療養費制度
- 限度額適用認定証
上記の制度は、健康保険や国民健康保険に加入している被保険者およびその被扶養者が対象です。
加入している健康保険の窓口で手続きについて相談してみましょう。
認知症で入院するときに気になるポイント

入院について考えるときに「本人が入院を拒否したら・・・」「退院できなかったらどうしよう」と思うことがあるかもしれません。
ここでは、そのような場合の対応をお伝えします。
入院を拒否する場合
認知症により本人が入院の必要性がわからない場合、入院を拒否されることが考えられます。
入院して治療が必要な場合は、本人の想いを受け止めながら、入院の必要性を繰り返し伝えましょう。
本人の同意を得ることが難しいうえで入院が必要な場合は、精神保健指定医の判断と保護者の同意のもと入院が可能な「医療保護入院」の適応となるケースもあります。
入院が長引く場合
認知症の方は、入院期間が長期化する傾向があります。
また、介護者がいなかったり社会資源が不足していたりなどの要因で退院が難しい場合もあります。
そのため、地域包括支援センターとの連携や介護サービスの確保などの支援体制が必要です。
- 介護者の有無
- 生活場所(自宅や施設など)
- 生活環境(デイサービスや介護サービスの利用など)
- 緊急時の対応
上記のポイントを事前に検討しておくと、スムーズに退院の段取りができるでしょう。
ケアマネジャーや地域包括支援センターで相談しながらすすめることができますよ。
まとめ
家族にとって認知症の方の入院に心配や不安を感じることがあるかもしれません。
ただし、入院して適切な治療を受けることは今後の生活において大切です。
また介護の負担は大きいため、ひとりで抱え込まないことが重要です。
「ベルコメンバーズアプリ」では、医療や介護のお悩み相談にのることができます。
悩みや不安は抱え込まず、まずは相談してみませんか。
コンシェルジュが丁寧にサポートします。
お気軽にご利用ください。
読まれている記事一覧
-

高齢者が同じことを何度も言うのはなぜ?対応方法と認知症との関連性を解説
-

認知症で病院に入院できる!精神科に入院する3つの基準や期間を解説
-

80代の親が少し前のことを忘れるのは単なる物忘れ?認知症との違いや見分ける方法を解説
-

高齢の親が寝てばかりいるのは認知症の初期症状が原因?家族ができる対処法3選
-

高齢の母親と話が通じない4つの理由|コミュニケーション改善法やストレス対策も解説
-

認知症の予防にはコミュニケーションが効果的!4つの方法も紹介
-

【無料プリントあり】認知症予防に役立つプリントの活用方法と選び方
-

認知症の原因物質であるアミロイドβとは?溜まる3つの原因や排出方法紹介
-

認知症の親を施設に入れるタイミングと注意点を徹底解説
-
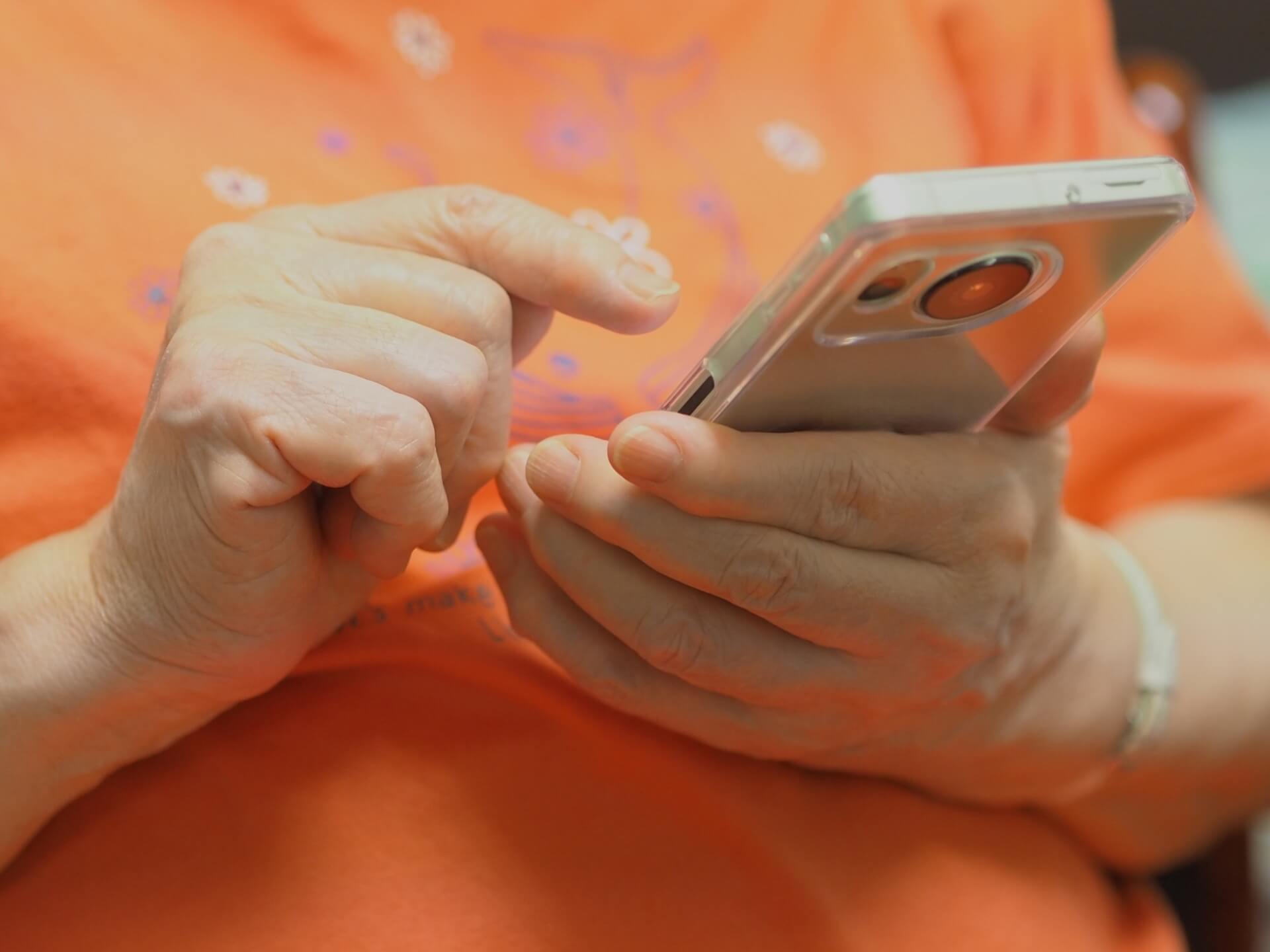
認知症予防に役立つチェックアプリ3選!おすすめポイントも紹介
-

認知症の症状を抑える方法は主に3つ!治った例や家族の対応ポイント
-

同じ話を繰り返す母親への対処法|2つの原因と認知症チェック方法も徹底解説
-

麻雀が認知症予防に?楽しみながら脳を使って健康に
-

英語を話せると認知症になりにくい?予防のための学習法をお伝えします
-

認知症の方への適切な接し方!ポイントと5つの具体例