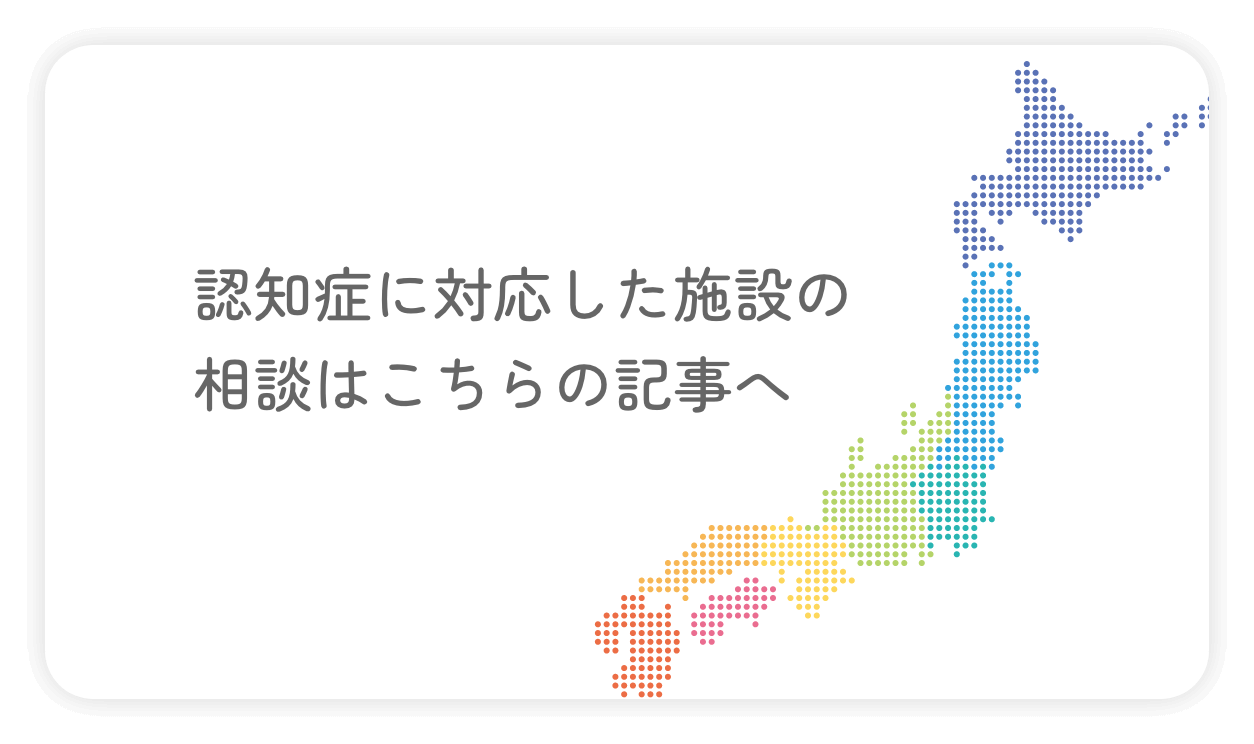認知症
認知症
 認知症
認知症
認知症の初期症状はわがまま?早く対処すべき3つの理由とその対処法

「最近、80代の母親がわがままを言うようになった」「わがままがひどくなったけど、これって認知症?」
このように困ったり不安になったりしていませんか。
もしかしたら、認知症の初期症状があらわれて「わがまま」と感じているのかもしれません。
このまま放置すると、認知症の症状が進行する恐れがあります。
この記事では、認知症の初期症状でわがままと感じる理由やその対処法などについて解説します。
自分の親がわがままとなり認知症ではないかと悩んでいるあなたの助けになれると幸いです。
Contents
認知症の初期症状はわがまま?4つの原因

認知症の症状には、以下のように大きく「2つ」に分けられます。
- 中核症状:記憶障害・見当識障害(日付や場所がわからなくなる)・理解力・判断力の低下など
- 行動・心理症状:不安・抑うつ・興奮・徘徊・易怒性など
これらの症状により、認知症の方はわがままと周囲の人から感じられることがあります。
ここでは、わがままと感じられる原因をくわしく紹介します。
⇒ 『認知症ともの忘れを見分ける方法とは?もの忘れがひどいときのチェック方法』
記憶障害があらわれる
認知症の初期症状のひとつに短期記憶の障害があります。
日常生活に支障はきたすほどではないものの、正常とも認知症とも言えない状態である軽度認知機能障害(MCI: Mild Cognitive Impairment)でも短期記憶の障害は起こります。
この短期記憶の障害により、最近の出来事や家族との予定などを忘れてしまうことが多くなるのです。
認知症の方が、同じ質問を何度も繰り返したり約束を守れなかったりした結果、家族や友人はこれを「わがまま」と感じることがあるかもしれません。
実際に、認知症の家族介護者2,358人に対する調査によると、認知症の家族を介護する方の「42.9%」は精神的な負担を感じているとされています。
この要因のひとつは、家族が「言っていることを理解してくれない」と思っている可能性があります。
そのため、彼らの行動が自己中心的に見えると言えるでしょう。
判断力が低下する
認知症になると判断力が低下します。
判断力が低下すると、普段の生活でさまざまなことを決められなくなります。
例えば、以下のようなケースがあります。
- 適切な洋服を選べない
- お金の管理ができない
- 外出しないと気が済まない
これらが、自己中心的な行動として家族に映ることもあります。
さらに、同じものばかりを食べたり、天候が悪いにも関わらず外出しようとしたりなど、強いこだわりがあらわれる場合もあります。
そのため、周囲には「わがまま」に見られるかもしれません。
感情のコントロールができなくなる
認知症の方は、感情のコントロールができなくなることで、些細なことに過度に反応する場合があります。
具体的には、以下のように反応します。
- 急に怒りっぽくなる
- 大声を出して怒りだす
- 目つきが変わり威嚇する
このような行動が家族によっては性格がきつくなったと感じるケースもあります。
認知症の方は感情のコントロールができなくなるため、自分の感情を理解し、それを適切に表現することが難しくなります。
このような情緒の不安定さは、周囲の人が「わがまま」と感じるきっかけになるでしょう。
新しい環境への適応が難しくなる
認知症になると、新しい環境や状況に適応するのが難しくなります。
というのも、環境の変化に対する不安や恐怖が背景にあり、これが行動に影響を与えるからです。
日常生活の中の変化に対して強い抵抗を示すことがあり、これを「わがまま」と捉えられる場合もあります。
新しい環境に適応しにくくなることは、認知機能の低下によって引き起こされるものであるため、家族や介護者の理解とサポートが必要と言えます。
認知症の初期症状のわがままに家族が早く対処すべき理由

認知症の方のわがままには早く対処したほうが良いです。
その理由は主に「3つ」あります。
- 家族や友人との関係悪化を防ぐ
- 認知症の方のこころが安定する
- 病状の進行を緩やかにできる
症状が進む前に認知症を発見できると、症状の進行を遅らせられる可能性があります。
認知症に似た病気や早く治療すると治る認知症(慢性硬膜下血腫、甲状腺機能低下症など)もあるため、認知症は早く発見することが重要です。
また、病気であると分かると家族や友人もわがままを理解しやすく、関係性の悪化を防げるかもしれません。
家族や友人との関係が保たれ適切な対応を受けられると、認知症の方はこころが安定するでしょう。
認知症であるか不安を感じている方は、下記の記事に診断チェックリストを用意しました。
ぜひ、チェックして自分の状況を確認してくださいね。
⇒ 『認知症テストの種類2つ!チェックリストを使って認知症を予防しよう』
まとめ
「わがまま」と感じたときは、認知症の症状があらわれている可能性があるため、早めに受診することが大切です。
ただし、先述した調査によると本人が違和感を覚えたり、家族が異変を感じてから診断に至るまでの期間は平均1年1か月としています。
つまり、1年以上適切な治療やケアを受けられないのです。
ただし、なかには病院に行くことに抵抗がある方がいるかもしれません。
まずは、「ベルコメンバーズアプリ」を活用してみてはいかがでしょうか。
お手軽に短時間でチェックでき、今の認知機能の状態を知ることができます。
下記のサイトからダウンロードしてみてくださいね。
監修者浦上 克哉教授

日本認知症予防学会代表理事、日本老年精神医学会理事、日本老年学会理事、日本認知症予防学会専門医
・1983年 鳥取大学医学部医学科卒業
・1988年 同大大学院博士課程修了
・1990年 同大脳神経内科・助手
・1996年 同大脳神経内科・講師
・2001年 同大保険学科生体制御学講座環境保健学分野の教授(2022年まで)
・2016年 北翔大学客員教授(併任)
・2022年 鳥取大学医学部保健学科認知症予防学講座(寄付講座)教授に就任
読まれている記事一覧
-

高齢者が同じことを何度も言うのはなぜ?対応方法と認知症との関連性を解説
-

認知症で病院に入院できる!精神科に入院する3つの基準や期間を解説
-

80代の親が少し前のことを忘れるのは単なる物忘れ?認知症との違いや見分ける方法を解説
-

高齢の親が寝てばかりいるのは認知症の初期症状が原因?家族ができる対処法3選
-

高齢の母親と話が通じない4つの理由|コミュニケーション改善法やストレス対策も解説
-

認知症の予防にはコミュニケーションが効果的!4つの方法も紹介
-

【無料プリントあり】認知症予防に役立つプリントの活用方法と選び方
-

認知症の原因物質であるアミロイドβとは?溜まる3つの原因や排出方法紹介
-

認知症の親を施設に入れるタイミングと注意点を徹底解説
-
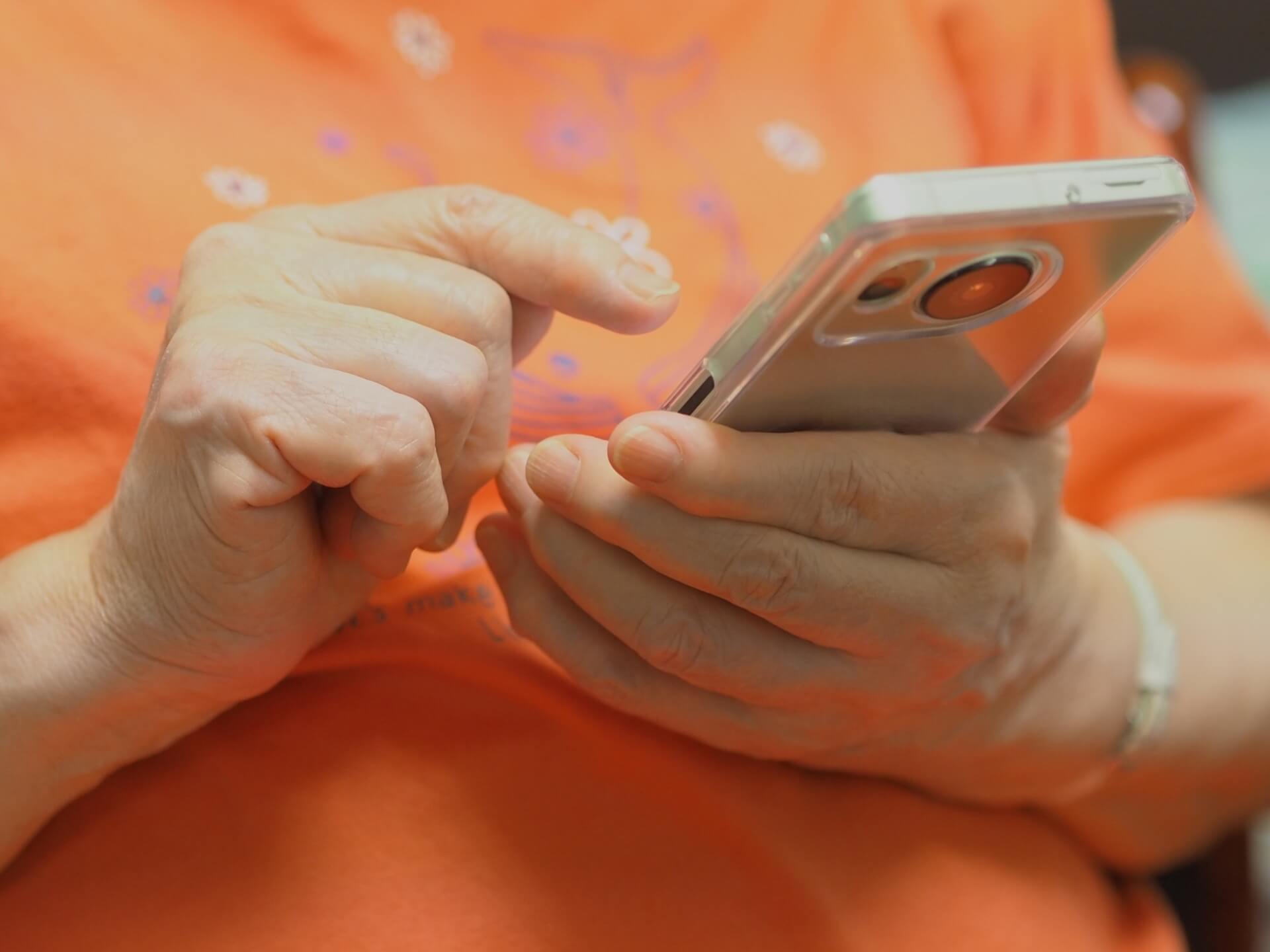
認知症予防に役立つチェックアプリ3選!おすすめポイントも紹介
-

認知症の症状を抑える方法は主に3つ!治った例や家族の対応ポイント
-

同じ話を繰り返す母親への対処法|2つの原因と認知症チェック方法も徹底解説
-

麻雀が認知症予防に?楽しみながら脳を使って健康に
-

英語を話せると認知症になりにくい?予防のための学習法をお伝えします
-

認知症の方への適切な接し方!ポイントと5つの具体例