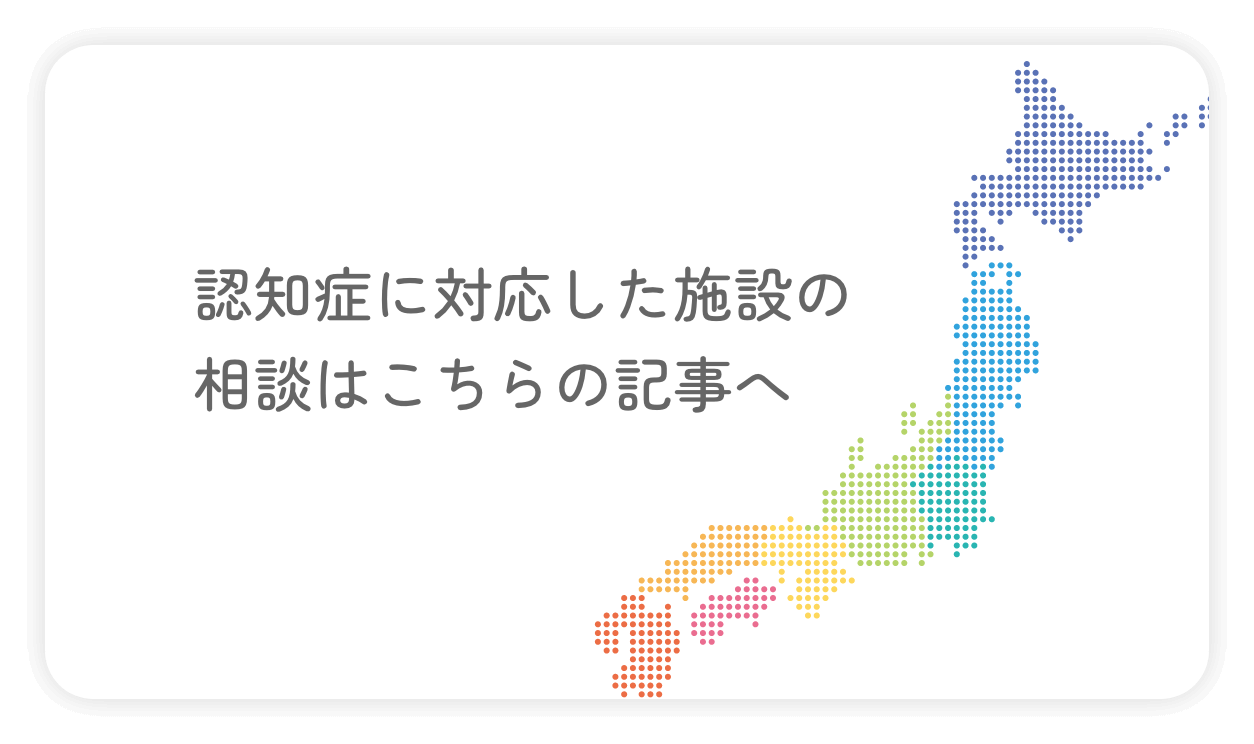認知症
認知症
 認知症
認知症
認知症の原因になりやすい食べ物3つ!予防になる食事メニューも紹介

「認知症になりやすい食べ物って何?」「認知症の予防になるメニューを知りたい」
このように不安や疑問を感じていませんか。
認知症は一度発症すると完治することは難しく、症状の進行を遅くすることが治療の目的です。
そのため、認知症は予防することが重要と言えます。
この記事では、認知症の原因になりやすい食べ物や予防につながるメニューを紹介します。
認知症と食べ物の関係が分からず、どのような食べ物を食べるべきか悩んでいるあなたの助けとなれれば幸いです。
Contents
認知症の原因になりやすい3つの食べ物

認知症の原因になりやすい食べ物を「3つ」解説します。
それぞれの食べ物を知って、認知症の予防につなげましょう。
『認知症ともの忘れを見分ける方法とは?もの忘れがひどいときのチェック方法』
⇒ 詳しくはこちら
加工された食べ物
認知症の原因になりやすい食べ物は、加工されたものです。
というのも、加工された食品には以下のような傾向があるからです。
- 高脂肪分
- 高糖分
- 高塩分
加工食品には、飽和脂肪酸が多く含まれており、これらの脂肪はLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を増加させ、動脈硬化が進む恐れがあります。
結果として、脳に酸素や栄養素がスムーズに行き渡りにくくなるため、認知症のリスクが高くなるのです。
また、砂糖や高果糖コーンシロップなどの多量の糖分が含まれ、高糖分の食品を摂取すると、急激な血糖値の上昇が引き起こされます。
長期間にわたって高血糖が続くと、糖尿病となり脳血管の健康を損ない、認知症の原因となります。
さらに、加工された食品に含まれる多量の塩分も認知症のリスクを高めると言えるでしょう。
高塩分の食品を摂取すると血管が収縮するため、血圧が上昇します。
高血圧は、脳血管の損傷や脳卒中のリスクを高め、認知症の発症リスクを増加させることがあります。
さまざまな理由により、加工された食品ばかりを食べると認知症になるケースがあるため、食べすぎには注意してくださいね。
トランス脂肪酸を多く含む食べ物
トランス脂肪酸を含む食べ物も認知症の原因になりやすいです。
トランス脂肪酸は、飽和脂肪酸の水素添加によって作られています。
これにより、食品の保存期間が長くなります。
ただし、同時にLDLコレステロールを増加させ、動脈硬化を引き起こす可能性があるのです。
動脈硬化が進むと、血管が硬くなることで弾力性がなくなり認知症のリスクが高まります。
そのため、買い物をするときには食品表示をチェックして食べ物を選びましょう。
糖分が多い食べ物
ソフトドリンクや果汁飲料には、高濃度の砂糖が含まれています。
これらの飲料を摂取することで、急激な血糖値の上昇が引き起こされます。
さらに、これらの飲料には栄養素がほとんど含まれておらず、エネルギー摂取が増えます。
その一方で、栄養が不足するため、肥満や糖尿病のリスクが高まり血管の健康が損なわれるでしょう。
その結果、認知症を発症する恐れがあります。
認知症の原因は食べるときの環境にもある

食べるときの環境も認知症の原因になる可能性があります。
というのも、誰かと一緒に食事する場合と比べて、ひとりで食事をする場合は認知機能の悪化に関連するとされているからです。
具体的には、以下のような食事の環境にしましょう。
- 誰かと一緒に食事をする
- 季節や行事を楽しみながら食事をする
- 五感を感じながら食事をする
ひとり暮らしの高齢者で誰かと一緒に食事することが難しい場合は、テレビ電話で話をしたり、地域のイベントに出たりして交流を持つようにしてくださいね。
認知症の予防になる食事メニュー

ここで、認知症の予防になる食事メニューを紹介します。
紹介するものを参考にして、普段の食事に役立ててくださいね。
栄養バランスの良い食事メニュー
野菜や魚、果物などを豊富に含む食事メニューが認知症の予防に期待できます。
というのも、アルツハイマー型認知症の方は脳内に酸化物が増加しており、野菜や果物などの抗酸化作用を持つ食品が予防に有効であるとされているからです。
たくさんの種類の食品を取ることで、認知機能が悪化するリスクを「44%」減らせます。
たとえば、以下のような食品を組み合わせたメニューにすると良いでしょう。
| 主食 | 主菜 | 副菜 | その他 |
|---|---|---|---|
| ・ごはん ・パン ・麺類 |
・肉 ・魚 ・卵 |
・豆類 ・サラダ ・煮物 |
・果物 ・ナッツ ・乳製品、お茶 |
出典元:あたまとからだを元気にする MCIハンドブック|国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
認知症の予防には、質の良い食事が大切であり、「主食と主菜」、「副菜と品目のバランス」が重要です。
塩分を控えた食事メニュー
塩分を控えた食事メニューは、認知症の予防につながる可能性があります。
というのも、塩分を摂取することで高血圧となり認知症になるリスクが高まるからです。
血圧が上がるほど、そのリスクは高まるとされています。
具体的には、以下のような方法をおこなうと減塩できるでしょう。
- 減塩タイプの食品を使う
- 加工食品や漬物はできるだけ使わない
- レモンや酢、香辛料などで塩分を避ける
- ラーメンやうどんなどの麺類の汁は残す
- 醤油やソースなどの調味料はかけずにつける
食事をする際に、これらを意識すると塩分を控えることができますよ。
適切なカロリーの食事メニュー
適切なカロリーの食事メニューも認知症の予防には欠かせません。
とくに、中年期には総コレステロール値が高いと、アルツハイマー型認知症になるかもしれません。
ただし、高齢期(65歳以上)では認知症と関連するとは明らかにされていません。
ただし、過度なカロリー制限は、栄養バランスが崩れたり、ほかの病気になったりする恐れがあります。
さらに、認知症の方によって適切なカロリーはそれぞれ異なります。
そのため、主治医や管理栄養士に適切なカロリーや食事のメニューを相談しましょう。
まとめ
加工された食品やトランス脂肪酸を多く含んだ食品などは認知症の原因となる恐れがあります。
主食や主菜などバランスの良い食事を心がけることが認知症の予防には欠かせません。
そこで、認知症の予防に役立つ「ベルコメンバーズアプリ」を利用してみませんか。
アプリに登録すると、コンシェルジュサービスも受けられるため、認知症の予防に関する悩みを解決できるでしょう。
監修者浦上 克哉教授

日本認知症予防学会代表理事、日本老年精神医学会理事、日本老年学会理事、日本認知症予防学会専門医
・1983年 鳥取大学医学部医学科卒業
・1988年 同大大学院博士課程修了
・1990年 同大脳神経内科・助手
・1996年 同大脳神経内科・講師
・2001年 同大保険学科生体制御学講座環境保健学分野の教授(2022年まで)
・2016年 北翔大学客員教授(併任)
・2022年 鳥取大学医学部保健学科認知症予防学講座(寄付講座)教授に就任
読まれている記事一覧
-

高齢者が同じことを何度も言うのはなぜ?対応方法と認知症との関連性を解説
-

認知症で病院に入院できる!精神科に入院する3つの基準や期間を解説
-

80代の親が少し前のことを忘れるのは単なる物忘れ?認知症との違いや見分ける方法を解説
-

高齢の親が寝てばかりいるのは認知症の初期症状が原因?家族ができる対処法3選
-

高齢の母親と話が通じない4つの理由|コミュニケーション改善法やストレス対策も解説
-

認知症の予防にはコミュニケーションが効果的!4つの方法も紹介
-

【無料プリントあり】認知症予防に役立つプリントの活用方法と選び方
-

認知症の原因物質であるアミロイドβとは?溜まる3つの原因や排出方法紹介
-

認知症の親を施設に入れるタイミングと注意点を徹底解説
-
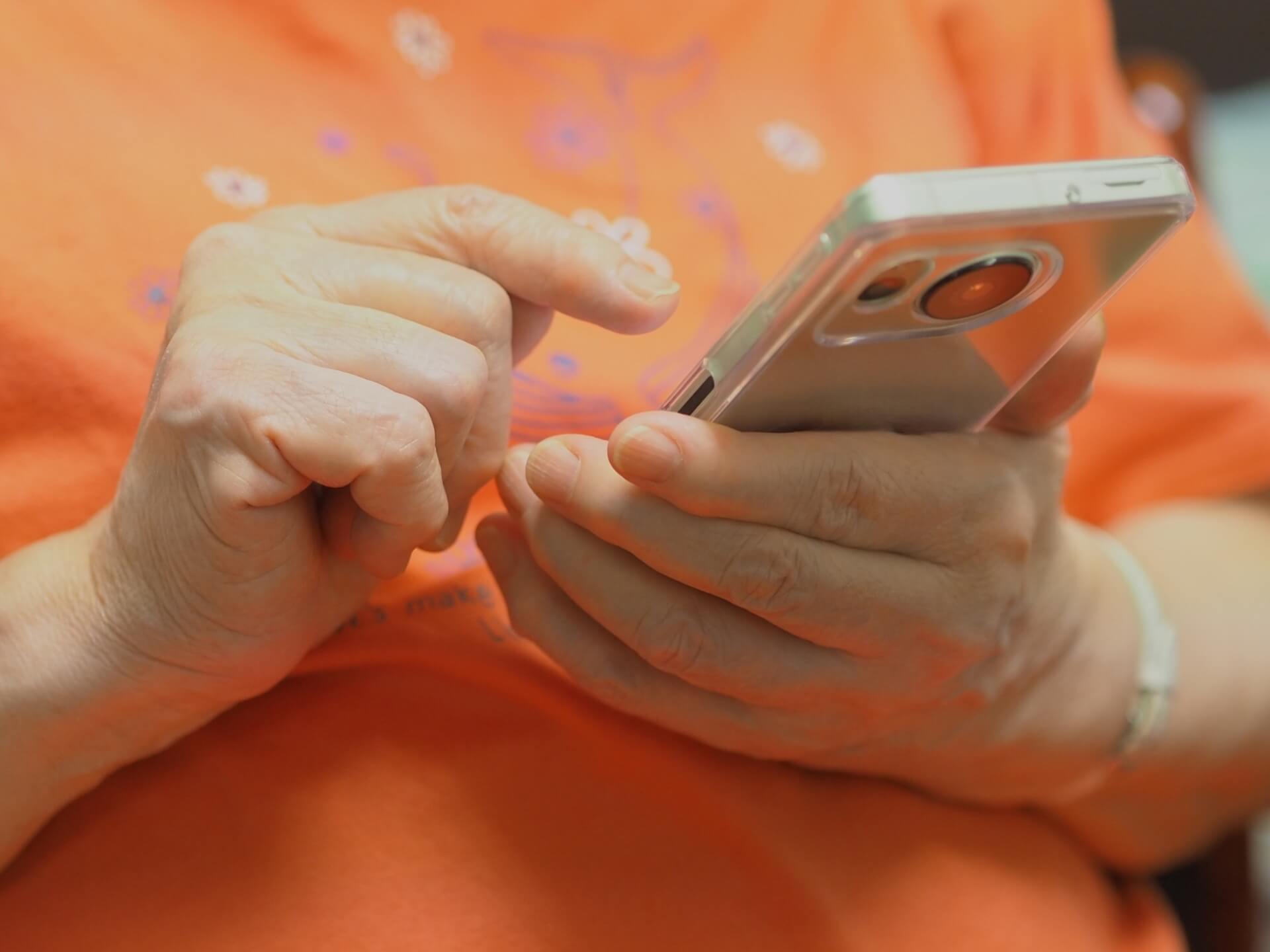
認知症予防に役立つチェックアプリ3選!おすすめポイントも紹介
-

認知症の症状を抑える方法は主に3つ!治った例や家族の対応ポイント
-

同じ話を繰り返す母親への対処法|2つの原因と認知症チェック方法も徹底解説
-

麻雀が認知症予防に?楽しみながら脳を使って健康に
-

英語を話せると認知症になりにくい?予防のための学習法をお伝えします
-

認知症の方への適切な接し方!ポイントと5つの具体例