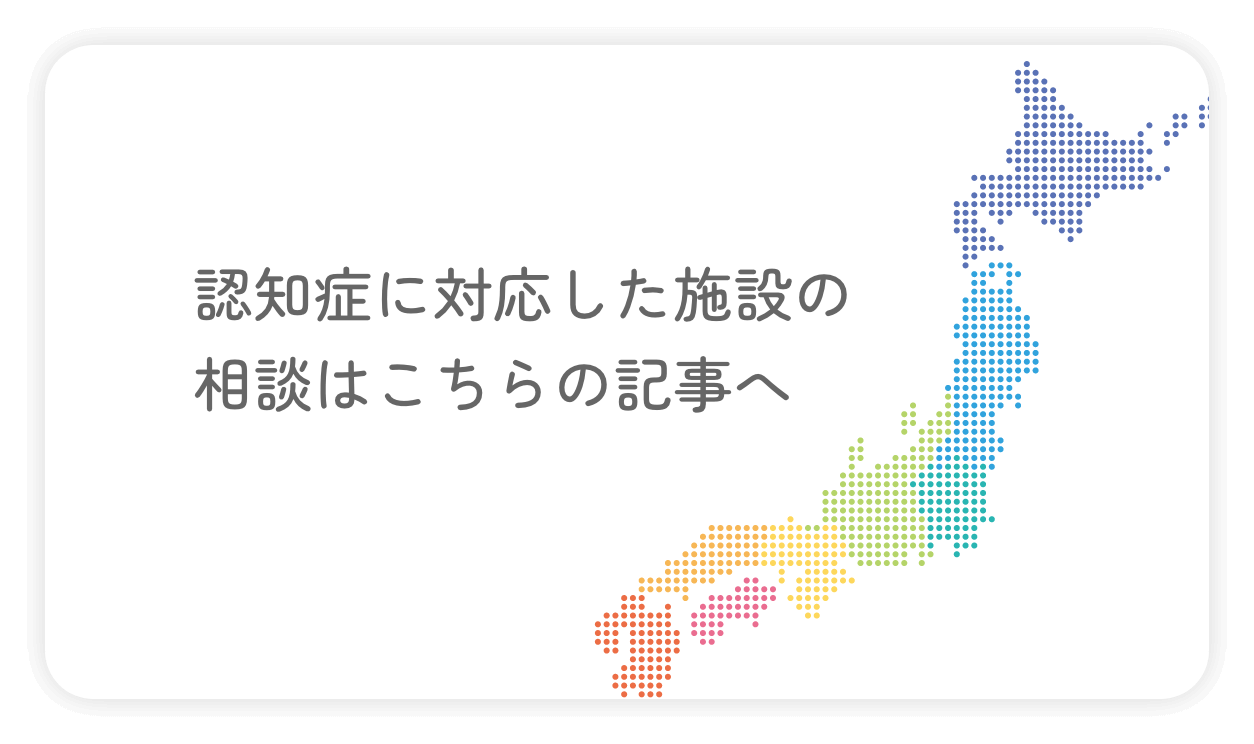認知症
認知症
 認知症
認知症
認知症予防に運動を!気軽にできる運動と実践ポイント
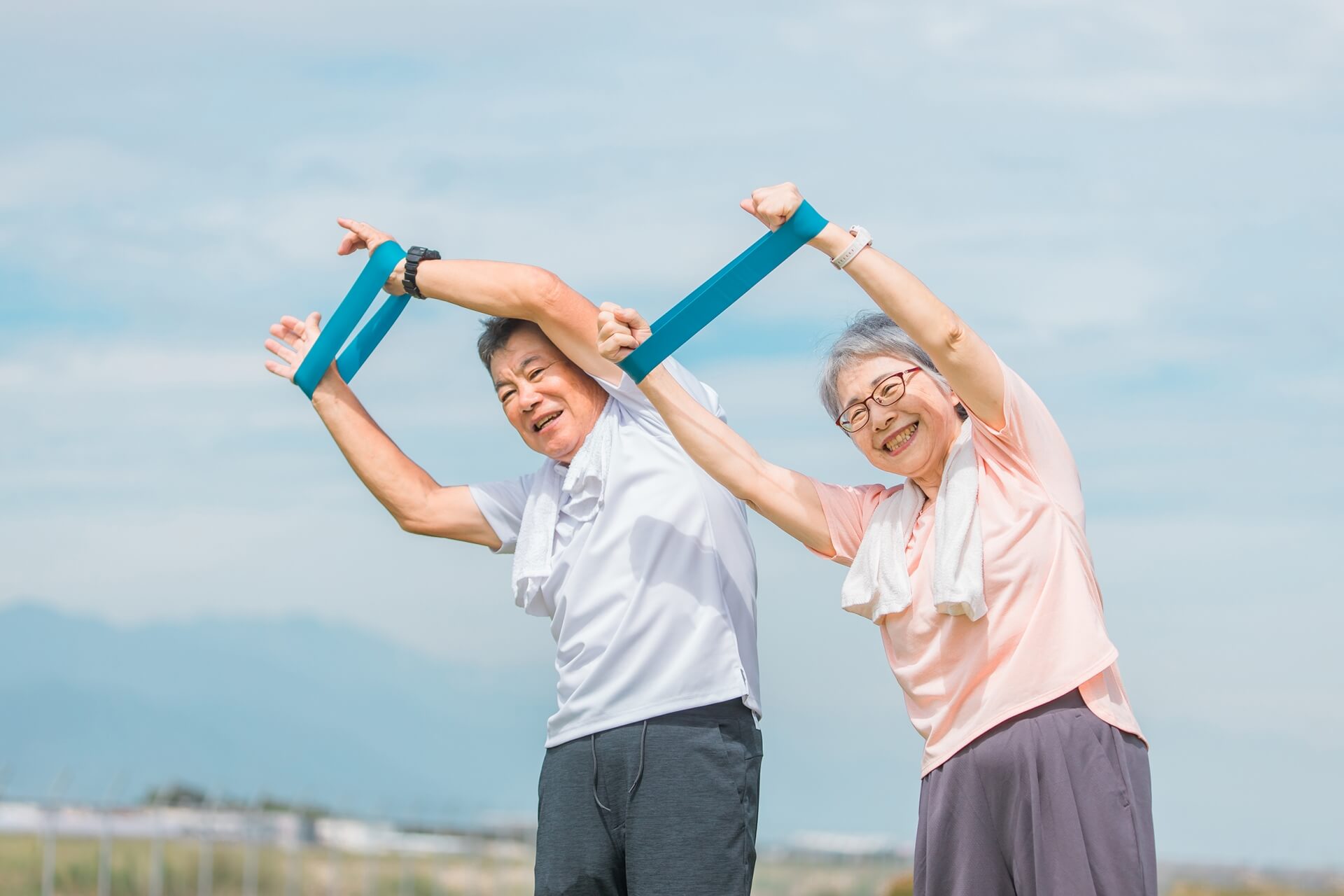
認知症予防に運動がよいと聞いたことはありませんか?
最近の研究によって、運動が認知症予防に効果的であることが示されています。
この記事では、誰でも気軽に始められる運動と、運動のポイントを詳しく紹介しています。
今から運動を始めてみようと思う方、すでに運動はしているけれども、より効率的な運動方法を知りたいという方はぜひ、チェックしてみてください。
Contents
運動がもたらす認知機能への影響

そもそも運動はなぜ認知症予防になるのでしょうか。
運動は身体が鍛えられるイメージですが、実は認知機能にもよい影響を与えます。
運動がもたらす認知機能への影響についてご紹介します。
記憶力の向上に役立つ
脳の記憶をつかさどる海馬では、神経細胞の成長や再生を促すBDNFというたんぱく質が神経細胞によって作り出されています。
運動をすると、このBDNFが活性化し、海馬を大きくして記憶力の向上に影響することがわかっています。
うつ症状を減らす
定期的な運動は、うつ症状やうつ病の発症リスクを低下させることがわかっています。
気分が落ち込む抑うつ状態になると、脳の働きが鈍り、神経に栄養が届きにくくなります。
その結果、認知機能低下につながりやすくなるのです。
そのため、定期的な運動で認知機能を維持することが大切です。
具体的な運動を4つ紹介

ここでは、気軽に行える認知症予防の運動を「4つ」紹介します。
ご自身にあった取り組みやすいものをチェックしてみてください。
どの運動もストレッチなどの準備運動をしてからはじめましょう。
ノルディックウォーキング
有酸素運動を行うことで「全般的な認知機能」、計画を立てて適切に実行する「実行機能」、言葉を理解したり表出したりする「言語」機能の改善が認められています。
有酸素運動といえばウォーキングがよく知られていますが、ポールを使った「ノルディックウォーキング」はご存じでしょうか。
ポールを使って歩くので、通常のウォーキングよりも大きな歩幅かつ、速いスピードで歩行でき、疲れにくいのが特徴です。
ポールの突き方や歩行スピードによっても身体にかかる負荷量が変化するので、自分にあったスピードや歩幅で始めてみましょう。
『認知症予防にウォーキング?歩き方のポイントと続けるためのコツ』
⇒ 詳しくはこちら
有酸素運動と筋トレの組み合わせ
有酸素運動に筋力トレーニング(以下、筋トレ)を合わせると、認知症予防の効果がより期待できるという報告があります。
有酸素運動は全身を使って一定時間以上続けて行える運動です。
ノルディックウォーキング・サイクリング・水中歩行・階段昇降などがあります。
運動中に楽に会話ができるくらいの運動強度(運動のきつさ)で取り組みましょう。
筋トレは週に2回以上の頻度で、大臀筋や大腿四頭筋、体幹筋(腹筋・背筋)などの身体の大きな筋肉を鍛えることが推奨されています。
主要な筋肉群を鍛えられる筋トレにはスクワット・つま先立ち・モンキーウォーク・腹筋などがあります。
「スクワット」「つま先立ち」「モンキーウォーク」の具体的な筋トレ方法はこちらの記事をご参照ください。
⇒ 『筋トレが認知症予防になる理由。簡単にできる3選と注意点を解説』
デュアルタスク
何かをしながら別の何かを行うことを「デュアルタスク」と言います。
テレビを見ながら料理する、電話をしながらメモを取る……といった「ながら運動」のことです。
認知症予防には、運動をしながら頭を使うデュアルタスクを行うと、記憶力が改善し、脳の萎縮を予防することがわかっています。
たとえば「ウォーキングをしながらしりとりをする」「サイクリングをしながら計算する」などがあげられます。
太極拳
ゆっくりとした動きで全身を使う太極拳。
足腰だけでなく体幹を含めた全身の筋力の向上が望めます。
ほかにもバランス能力の向上や痛みの軽減が期待できます。
研究結果では週3回の太極拳で、一部の認知機能によい影響を与えることが示唆されました。
太極拳のレッスン動画などをみながら自宅でも気軽に取り組めそうですね。
運動効果を得られやすくするためのポイント

運動の効果を得られやすくするためのポイントをまとめました。
運動を行うときの参考にしてみてください。
少しきついくらいがちょうどよい
運動をやり過ぎて身体を痛めてしまうと、日常生活に支障をきたすことがあります。
週3日以上の運動頻度が推奨されていますが、最初は無理のない範囲で実施し、徐々に増やしていきましょう。
また、痛みや持病がある場合は、かかりつけ医の先生に相談してから取り組みましょう。
日常生活の中に運動を取り入れる
運動する時間を作るのが難しければ、生活の中に運動を取り入れるのもよいでしょう。
1日10~20分程度の中強度以上の運動でも認知機能の改善が期待できると言われています。
中強度以上の運動とは、次のような3メッツ(身体活動の強度を表す単位)以上の運動です。
- 歩く(3.0メッツ)、やや速歩き(4.3メッツ)
- 自転車をこぐ(4.0メッツ)
- 階段を上がる(4.0メッツ)
- 動物と遊ぶ(5.0メッツ) など
「速いペースで歩く」「エレベーターを使わずに階段をのぼる」「電車ではなく自転車で移動する」など、普段の生活の中で歩く機会を増やし、「今よりも身体を積極的に動かす」ように意識しましょう。
継続できる環境を作る
運動は続けることで認知症予防につながります。
1人での継続が難しければ、家族や友人などを交えて実施するのもおすすめです。
変化を共有でき、モチベーションの維持にもつながるでしょう。
運動を継続して認知症を予防しよう
自分に合った運動を継続し、認知症予防に努めていきましょう。
また、認知機能を継続的にチェックすることも大切です。
「ベルコメンバーズアプリ」は、質問に答えるだけで、短時間で現在の認知機能を簡単にチェックできます。
さらに無料登録で、過去の結果も確認でき、前回との比較も行えます。
認知機能チェックは、アプリのインストールのみで利用できますので、認知症予防に役立ててください。
読まれている記事一覧
-

高齢者が同じことを何度も言うのはなぜ?対応方法と認知症との関連性を解説
-

認知症で病院に入院できる!精神科に入院する3つの基準や期間を解説
-

80代の親が少し前のことを忘れるのは単なる物忘れ?認知症との違いや見分ける方法を解説
-

高齢の親が寝てばかりいるのは認知症の初期症状が原因?家族ができる対処法3選
-

高齢の母親と話が通じない4つの理由|コミュニケーション改善法やストレス対策も解説
-

認知症の予防にはコミュニケーションが効果的!4つの方法も紹介
-

【無料プリントあり】認知症予防に役立つプリントの活用方法と選び方
-

認知症の原因物質であるアミロイドβとは?溜まる3つの原因や排出方法紹介
-

認知症の親を施設に入れるタイミングと注意点を徹底解説
-
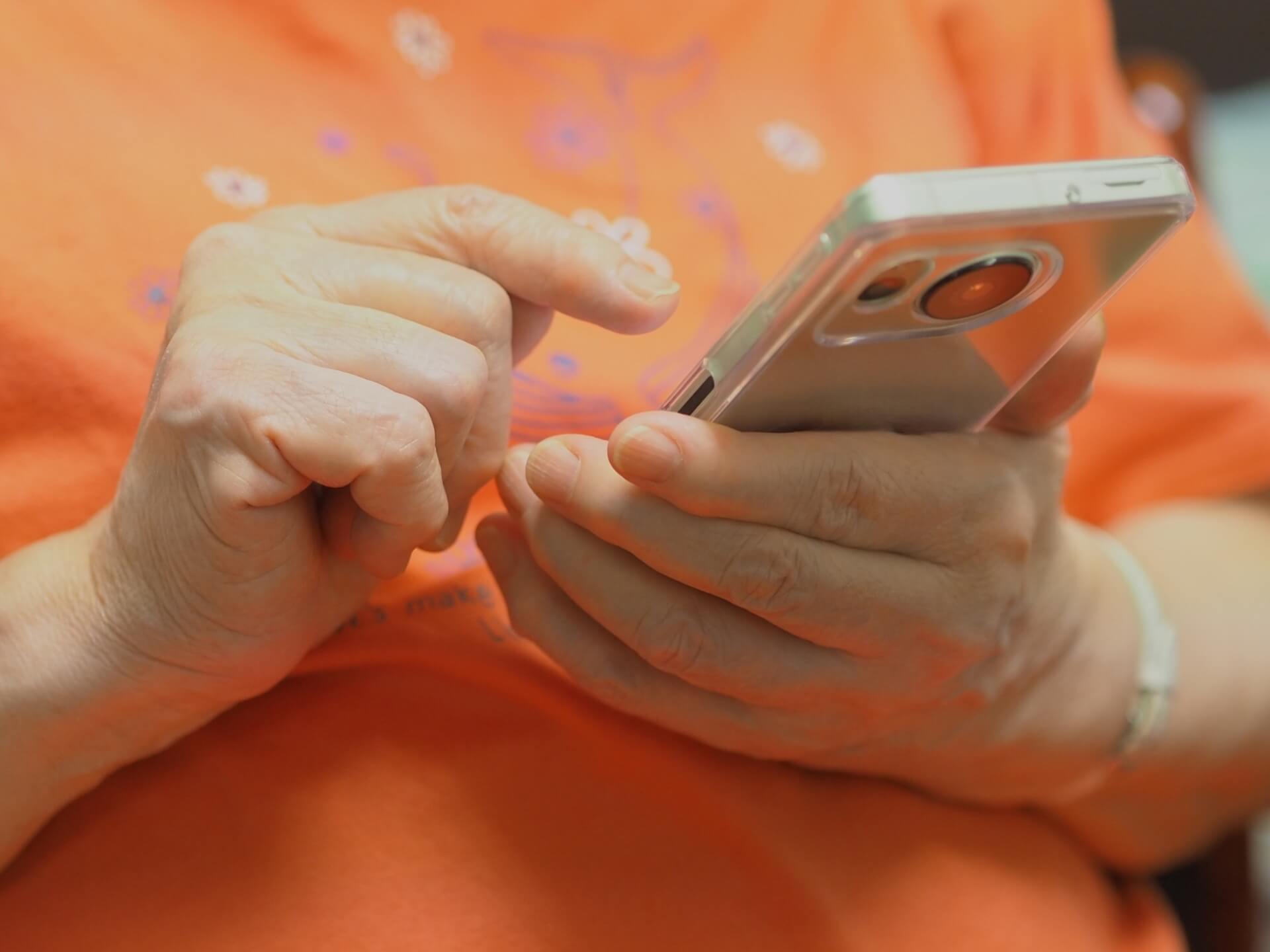
認知症予防に役立つチェックアプリ3選!おすすめポイントも紹介
-

認知症の症状を抑える方法は主に3つ!治った例や家族の対応ポイント
-

同じ話を繰り返す母親への対処法|2つの原因と認知症チェック方法も徹底解説
-

麻雀が認知症予防に?楽しみながら脳を使って健康に
-

英語を話せると認知症になりにくい?予防のための学習法をお伝えします
-

認知症の方への適切な接し方!ポイントと5つの具体例