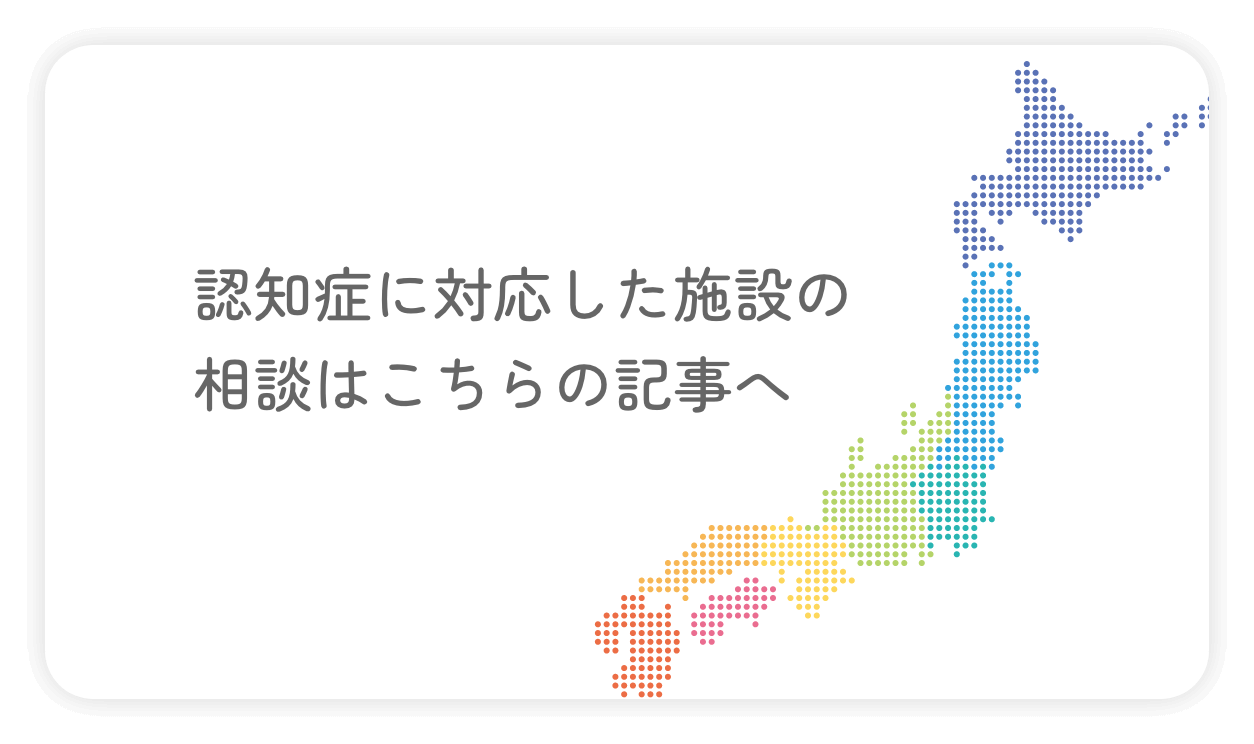認知症
認知症
 認知症
認知症
認知症予防のためのリハビリの種類と受けられる場所

認知症予防のための運動はよく知られていますが、認知症予防のリハビリとはどのようなものなのでしょうか?
認知症予防のリハビリについて、対象となる人や目的を説明し、具体的なリハビリの種類を紹介しています。
受けられる場所についても記載していますので、今から認知症予防に取り組みたい方はチェックしてみてください。
Contents
認知症予防のリハビリの対象と目的

リハビリテーション(以下、リハビリ)と聞くと、筋トレや歩行練習など、身体の不自由な人が行うものを想像する人が多いかもしれません。
ここでは「認知症予防のリハビリ」について、その対象と目的を詳しく説明します。
リハビリは健康な人も対象
リハビリは病気やケガをした人が回復をめざして行う運動や練習というイメージが一般的かもしれません。
しかし、WHOはリハビリテーションを「あらゆる年齢層のすべての人々の健康な生活を確保し、ウエルビーイングの促進を達成するための重要な戦略」と位置づけています。
さらに「リハビリが有効な健康な人々は世界中で24億人いる」としています。
日本においても、高齢化が進む中で、「介護が必要な状態となるのは特別なことではなく、リハビリは誰にでも必要なもの」とされています。
つまり、リハビリは病気やケガをした人だけでなく、健康な人にも必要なのです。
目的は認知症になるのを遅らせる
「予防」というと「病気にならないようにする」と捉えられがちですが、認知症予防では「認知症になるのを遅らせる」「認知症の進行を緩やかにする」という意味で使用されます。
認知症と診断された後に医療機関や介護施設で行われる運動療法、音楽療法、回想法、作業療法(認知機能に働きかける個別プログラム、ADL訓練)、レクリエーションなどのリハビリは、認知症の症状の改善や日常生活動作の低下予防を目的としています。
認知症では、健康なときから取り組む「認知症になるのを遅らせる」予防が重要です。
リハビリ内容としては「こころ・身体・社会」の3つの側面を整え、「自分らしい暮らし」につながる「活動」「参加」を視野に入れたプログラムであることが大切とされています。
いつから取り組めばよいかは「認知症 予防 いつから」の記事で詳しく説明しています。
⇒ 『認知症予防はいつから始めるべき?始めるタイミングと5つの予防法』
認知症予防のリハビリの種類
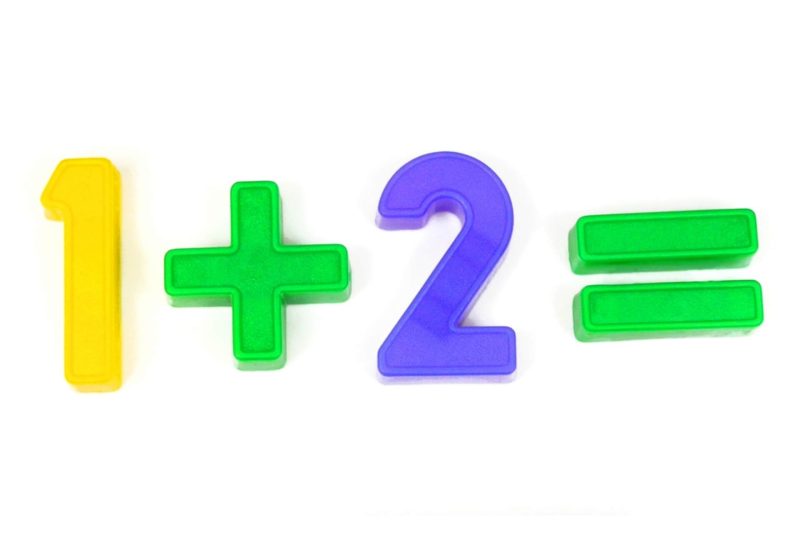
認知症予防のリハビリは、多くの自治体で取り組まれています。
その内容は運動療法、知的活動、運動と認知課題を合わせた活動などがあります。
ここでは、健康な状態から取り組みたいリハビリプログラムを紹介していきます。
運動療法
運動は脳の神経栄養因子(脳機能の改善に役立つタンパク質)を作り出し、記憶をつかさどる海馬領域の変化をもたらして、認知機能の低下を遅らせると言われています。
さらに、身体活動の向上や睡眠の質の改善、目標の達成・社会参加の機会の増加などにもつながります。
認知症のリスクを高める糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の予防にも有効です。
認知症予防のリハビリとして取り組まれている運動を紹介します。
- 準備運動としてのストレッチ
- 有酸素運動(ポールウォーキング、ウォーキング、足踏み、ステップ台昇降、エアロビクスなど)
- 筋力トレーニング
認知症予防のためのウォーキング、筋トレ、運動については次の記事で具体的なエクササイズを紹介しています。
⇒ 『認知症予防にウォーキング?歩き方のポイントと続けるためのコツ』
⇒ 『筋トレが認知症予防になる理由。簡単にできる3選と注意点を解説』
⇒ 『認知症予防に運動を!気軽にできる運動と実践ポイント』
知的活動
知的活動とは、記憶や注意、遂行力などの認知機能を意識した活動です。
活動によって使われる認知機能が異なるため、複数の活動に取り組むことが推奨されています。
自治体でも認知症予防として取り組まれている知的活動をいくつか挙げます。
- 記憶力ゲーム
記憶力を刺激する知的活動、記憶に関連する脳血流の増加や脳内ネットワークの活性化につながります。 - 間違い探し、文字探し、迷路
複数のことに同時に注意を向ける、多くの情報から必要な情報を選択する、1つのことを長く続けるなどの注意機能が必要です。 - クロスワードパズル
作業や動作に必要な情報を一時的に記憶して処理する作業記憶(ワーキングメモリー)を刺激します。 - 貼り絵、塗り絵
目から入った視覚的情報を処理し、空間の全体的なイメージをつかむための視空間認知機能に焦点をあてた活動です。 - カレンダーづくり
遂行力を刺激する活動です。 - 麻雀やチェスなどのボードゲーム
定期的に行うことで、全般的認知機能や記憶力の維持・改善が認められたという報告があります。
グループで活動に取り組むとコミュニケーションも促されます。
ほかにも英会話、俳句、音楽などの趣味活動も知的活動の1つです。
認知症予防の英語についてはこちらで学習方法も紹介しています。
⇒ 『英語を話せると認知症になりにくい?予防のための学習法をお伝えします』
認知症予防のためのプリント課題はこちらからダウンロードしていただけます。
⇒ 『【無料プリントあり】認知症予防に役立つプリントの活用方法と選び方』
認知症予防の麻雀はこちらでも詳しく解説しています。
⇒ 『麻雀が認知症予防に?楽しみながら脳を使って健康に』
コグニサイズ
「コグニサイズとは国立長寿医療研究センターが開発した運動と認知課題を組み合わせた、認知症予防を目的とした取り組みのこと」です。(引用:国立長寿利用研究センター作成パンフレット.認知症予防に向けた運動 コグニサイズ)
コグニサイズには、以下のようなプログラムがあります。
- コグニウォーク:しりとり、計算などの課題をやりながらウォーキング
- コグニステップ:数を数えながらステップを踏み、決まった倍数で拍手をする
- コグニラダー:はしご上のロープのマス目に決まった法則で足を入れ、ステップを踏む
コグニサイズ パンフレット【PDF】
引用:国立長寿利用研究センター作成パンフレット.認知症予防に向けた運動 コグニサイズ
認知症予防のリハビリを受けられる場所

認知症予防のリハビリは、ご家庭で個人でも取り組めますが、自治体の公民館などで開催されているリハビリプログラムに参加できる場合もあります。
鳥取県伯耆町では鳥取大学医学部浦上克哉教授らが開発した「とっとり式認知症予防プログラム」が作業療法士などによって開催されています。
ほかの自治体では「介護予防教室」「脳活フェスタ」「スマイルエイジ教室」「元気はつらつ塾」「健康シニア応援塾」などの名称で開催されている例もありますので、興味のある方はお住まいの自治体のホームページや広報誌などをチェックしてみてください。
リハビリと合わせて認知機能チェックで早期発見
認知症は誰でもなる可能性がある病気です。
認知症予防のリハビリに取り組むと同時に、認知機能チェックを定期的に行って、早期発見につなげましょう。
「ベルコメンバーズアプリ」は、スマホで簡単に認知機能をセルフチェックできるアプリです。
登録なしでチェックができ、無料登録で詳しい結果を確認できます。
変化にいち早く気付き対処することが大切ですので、認知症予防のリハビリと合わせて取り組んでみてはいかがでしょうか。
読まれている記事一覧
-

高齢者が同じことを何度も言うのはなぜ?対応方法と認知症との関連性を解説
-

認知症で病院に入院できる!精神科に入院する3つの基準や期間を解説
-

80代の親が少し前のことを忘れるのは単なる物忘れ?認知症との違いや見分ける方法を解説
-

高齢の親が寝てばかりいるのは認知症の初期症状が原因?家族ができる対処法3選
-

高齢の母親と話が通じない4つの理由|コミュニケーション改善法やストレス対策も解説
-

認知症の予防にはコミュニケーションが効果的!4つの方法も紹介
-

【無料プリントあり】認知症予防に役立つプリントの活用方法と選び方
-

認知症の原因物質であるアミロイドβとは?溜まる3つの原因や排出方法紹介
-

認知症の親を施設に入れるタイミングと注意点を徹底解説
-
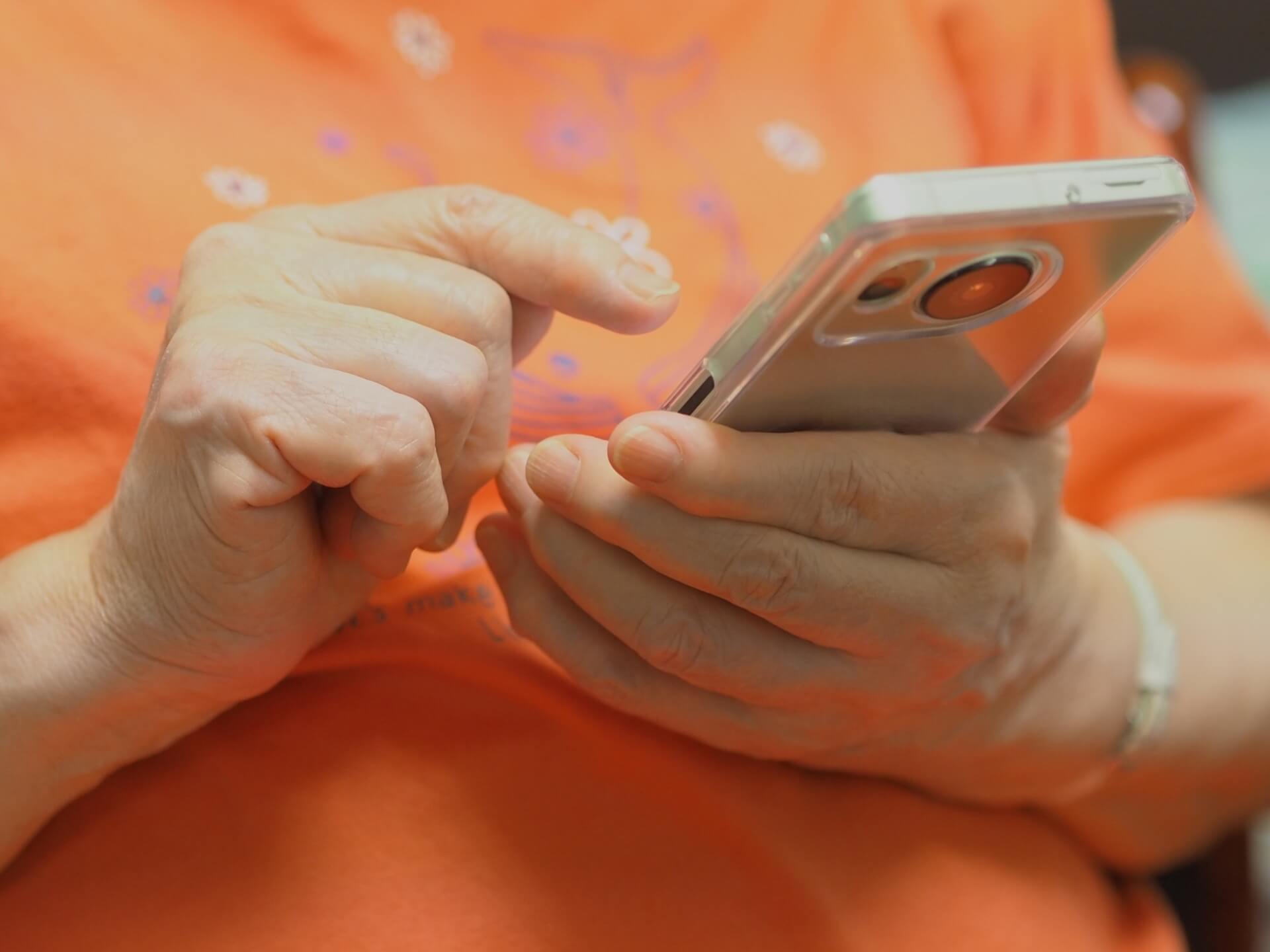
認知症予防に役立つチェックアプリ3選!おすすめポイントも紹介
-

認知症の症状を抑える方法は主に3つ!治った例や家族の対応ポイント
-

同じ話を繰り返す母親への対処法|2つの原因と認知症チェック方法も徹底解説
-

麻雀が認知症予防に?楽しみながら脳を使って健康に
-

英語を話せると認知症になりにくい?予防のための学習法をお伝えします
-

認知症の方への適切な接し方!ポイントと5つの具体例