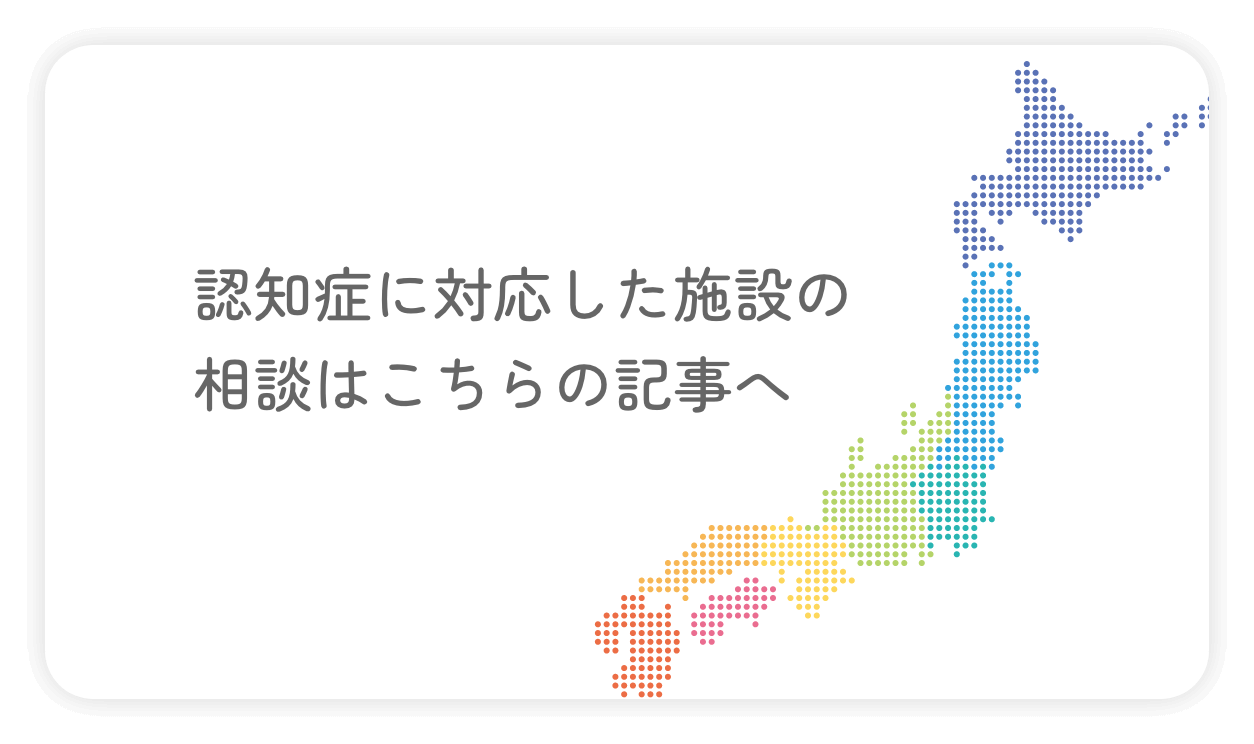認知症
認知症
 認知症
認知症
親が認知症かも…確認すべき5つの初期症状と相談先!今すぐチェックできる方法も紹介

親のもの忘れがひどくなり「もしかして認知症かも」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
認知症は早期の発見が重要といえます。
初期症状を見逃さず早めに対応することで、進行を遅らせることも可能だからです。
ここでは、認知症の初期症状として確認すべきポイントや、相談先について詳しく解説します。
また、認知症チェックが簡単にできるアプリについても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
親が認知症かも…?チェックすべき5つの初期症状

ここでは、認知症の初期症状として「チェックすべき点」について見ていきましょう。
1.もの忘れがひどくなる
認知症の最も一般的な初期症状はもの忘れです。
通常のもの忘れと異なり、認知症の場合は最近の出来事や会話の内容をすぐに忘れることが特徴です。
また、同じ質問を何度も繰り返したりすることが増えます。
たとえば、以下のようなことです。
- 食事を済ませたばかりなのに「昼ご飯を食べたかな?」と何度も聞く
- 「今日は何曜日?」と数分おきに質問する
もの忘れは日常生活に支障をきたし、対応する家族にとっても負担になります。
対処法についてはこちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
⇒ 『同じ話を繰り返す母親への対処法|2つの原因と認知症チェック方法も徹底解説』
2.時間や場所が分からなくなる
認知症の初期には、時間や場所に関する感覚が鈍くなることがあります。
また、自宅内でも部屋の配置や物の位置が分からなくなり、混乱することが増えてきます。
たとえば、以下のようなことです。
- 日時が分からなくなる
- 知っているはずの道で迷子になる
- 長年使っているリモコンの使い方がわからなくなる
3.判断力や理解力が低下する
日常生活の中で、判断力や理解力が低下するのも認知症の初期症状のひとつ。
たとえば、以下のようなことです。
- 電気代や水道代の支払いを忘れる
- 銀行の振込手続きができなくなる
また、話の流れを理解するのが難しくなり、会話が途切れがちになることもあります。
趣味のサークルなどに参加しても会話に追いつけないため、次第に社会的な活動への参加意欲が失われがちになります。
4.身の回りのことができなくなる
認知症の初期には、日常的な身の回りのことができなくなることがあります。
衣服の選び方が適切にできなくなり、季節に合わない服装をすることもあります。
たとえば、以下のようなことです。
- 料理の途中で何をしていたのかを忘れ、火をつけたまま放置する
- 洗濯物を干し忘れる
- 真夏に厚手のセーターを着たり、冬に薄手のシャツだけで過ごそうとしたりする
健康にも悪影響を及ぼす可能性があるため、家族が注意深く見守る必要があるでしょう。
5.感情の起伏が激しくなる
突然怒り出したり泣き始めたりと、これまで見られなかった感情の起伏が現れることがあります。
たとえば、以下のようなことです。
- 親しい友人に対して急に怒鳴る
- テレビの音量が少し大きいだけで不機嫌になる
家族や友人との関係が難しくなることがあるため、認知症の初期症状の可能性があることを理解しておくことが重要です。
親が認知症かもしれないと感じたときの4つの相談先

親が認知症かも…と悩んだときは、ひとりで悩まず早めに相談することが大切です。
症状が軽い段階であれば、薬で進行を遅らせることも可能だからです。
ここでは、「4つの相談先」を紹介します。
1.地域包括支援センター
地域包括支援センターは認知症に関する情報や支援を提供してくれる公的な機関で、すべての市町村に設置されています。
専門的なアドバイスを受けることで、初期対応における不安を軽減できるでしょう。
詳しくは、厚生労働省の地域包括ケアシステムのページをご確認ください。
2.電話相談
電話相談は簡単に利用できるため、初期段階での相談に適しています。
電話相談を受け付けている機関では、認知症に関する知識やコミュニケーションの方法などについて、専門家によるアドバイスが受けられます。
詳しくは、厚生労働省の認知症に関する相談窓口のページからご確認ください。
3.医療機関
認知症の疑いがある場合、親の健康状態をよく理解しているかかりつけ医やもの忘れ外来を受診しましょう。
もの忘れ外来は、認知症の早期発見と診断を専門とし、診断に必要な検査の実施や治療計画が立てられます。
もの忘れ外来は、全国もの忘れ外来一覧から検索可能です。
4.認知症カフェ・家族の会
認知症カフェや家族会などに参加してみることもおすすめです。
同じような悩みを抱える家族や介護者と交流することができるからです。
悩みを共有したり情報を交換したりすることで、精神的な支えが得られるだけでなく、具体的な対応策やケアについて知識を深められます。
詳しくは、お住いの市町村の高齢者福祉担当課や地域包括支援センターにお問合せください。
親が認知症かも…と思ったら、今すぐ認知症アプリでチェック
親が認知症かもしれないと感じたら、まずは手軽にできる認知症アプリでチェックしてみましょう。
「ベルコメンバーズアプリ」の認知機能チェックは、認知症の初期症状を確認するための簡単な質問に答えるだけで、症状の傾向や進行度を短時間で把握できます。
認知症アプリでの診断結果をもとに、地域包括支援センターや医療機関でより具体的な相談ができることも大きなメリットです。
専門家との相談がスムーズに進み、適切なアドバイスを受けやすくなります。
まずは、こちらからアプリをダウンロードし、今すぐチェックしてみてください。
監修者浦上 克哉教授

日本認知症予防学会代表理事、日本老年精神医学会理事、日本老年学会理事、日本認知症予防学会専門医
・1983年 鳥取大学医学部医学科卒業
・1988年 同大大学院博士課程修了
・1990年 同大脳神経内科・助手
・1996年 同大脳神経内科・講師
・2001年 同大保険学科生体制御学講座環境保健学分野の教授(2022年まで)
・2016年 北翔大学客員教授(併任)
・2022年 鳥取大学医学部保健学科認知症予防学講座(寄付講座)教授に就任
読まれている記事一覧
-

高齢者が同じことを何度も言うのはなぜ?対応方法と認知症との関連性を解説
-

認知症で病院に入院できる!精神科に入院する3つの基準や期間を解説
-

80代の親が少し前のことを忘れるのは単なる物忘れ?認知症との違いや見分ける方法を解説
-

高齢の親が寝てばかりいるのは認知症の初期症状が原因?家族ができる対処法3選
-

高齢の母親と話が通じない4つの理由|コミュニケーション改善法やストレス対策も解説
-

認知症の予防にはコミュニケーションが効果的!4つの方法も紹介
-

【無料プリントあり】認知症予防に役立つプリントの活用方法と選び方
-

認知症の原因物質であるアミロイドβとは?溜まる3つの原因や排出方法紹介
-

認知症の親を施設に入れるタイミングと注意点を徹底解説
-
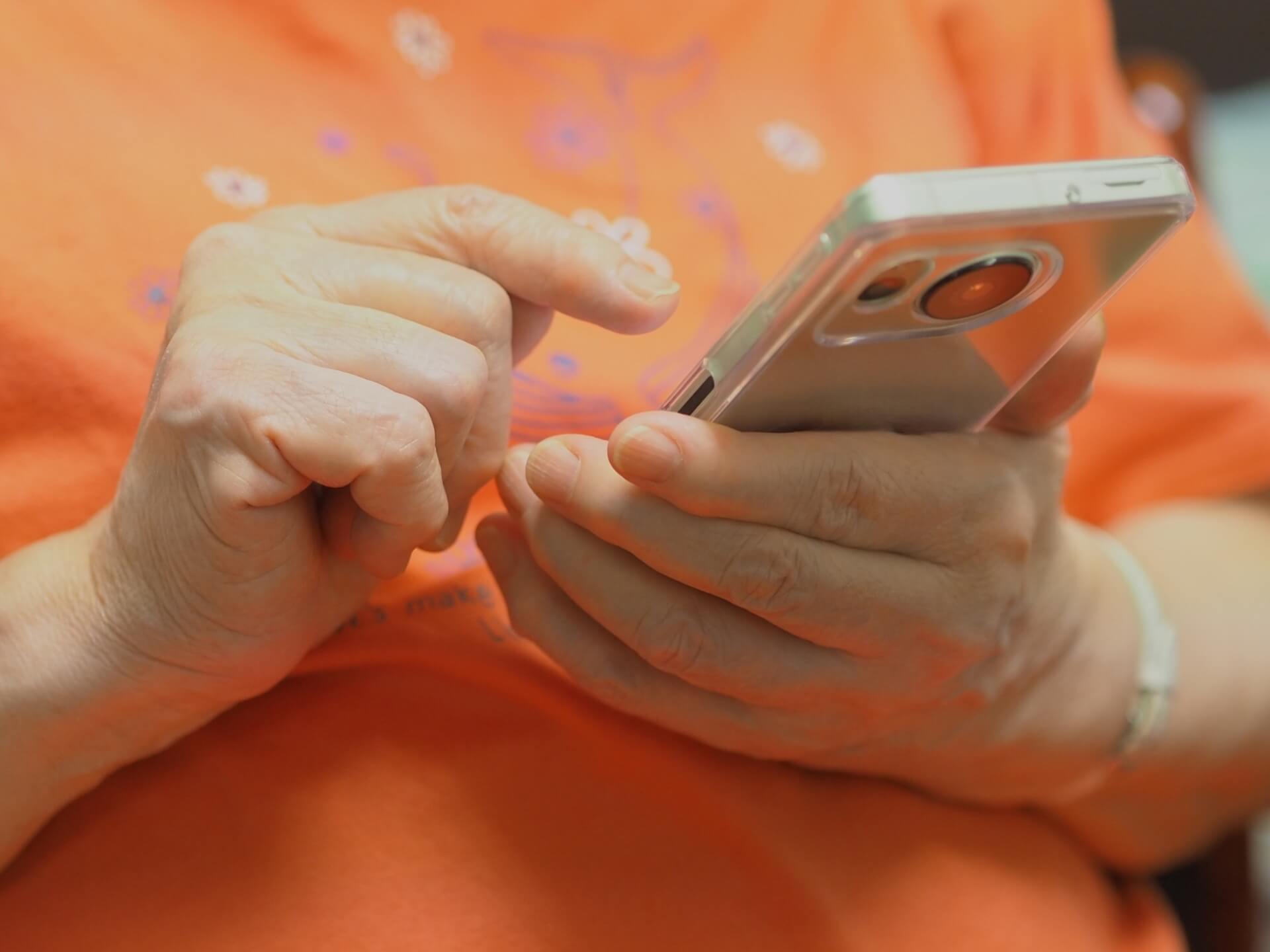
認知症予防に役立つチェックアプリ3選!おすすめポイントも紹介
-

認知症の症状を抑える方法は主に3つ!治った例や家族の対応ポイント
-

同じ話を繰り返す母親への対処法|2つの原因と認知症チェック方法も徹底解説
-

麻雀が認知症予防に?楽しみながら脳を使って健康に
-

英語を話せると認知症になりにくい?予防のための学習法をお伝えします
-

認知症の方への適切な接し方!ポイントと5つの具体例